この本を知るきっかけは、第二著者であるアシュリー・メリーマンと2008年に子ども発達学会(SRCD: Society for Research in Child Development)で出会ったことに始まります。この会議は米国で2年に一度の割合で開催され、世界各地からの参加者が集まる大規模な国際会議です。私が発表した専門家による子育ての助言に関する日米比較研究に興味を持ったメリーマン氏からいろいろと質問を受けたのですが、後の名刺交換で、近々発売されるこの図書について知りました。
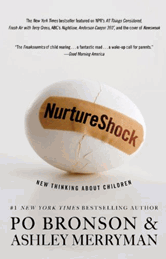
NurtureShock: New Thinking About Children
by Po Bronson, Ashley Merryman,
Grand Central Publishing, 2009
メリーマン氏は、ジャーナリスト兼弁護士で、クリントン政権のもとでスピーチライターを務めた経験の持ち主です。第一著者のジャーナリスト兼ライターであるポー・ブロンソン氏は、『このつまらない仕事を辞めたら、僕の人生は変わるのだろうか?(What should I do with my life?)』というニューヨーク・タイムズベストセラーNo.1に輝いた本の作者です。『NurtureShock』のもとになった子育てに関する記事は、米国科学振興協会の雑誌ジャーナリズム賞、現代家族評議会のジャーナリズム優秀賞など、数多くの賞を受賞しています。日本でも、『間違いだらけの子育て―子育ての常識を変える10の最新ルール』と題した翻訳がインターシフト社より2011年に出版されていますので、その訳に沿いながら紹介してみたいと思います。
この本の特徴は、数多くの研究データを引用しながら紹介することで、子育ての常識として浸透している様々な定説に新たな知見をもたらしているところでしょうか。「ほめて伸ばす」「子どもの嘘」「きょうだい喧嘩」「ギフテッド教育」などの子育て真っ盛りの親に関心の高いテーマが選択されていますが、特に私が関心を持った2つのテーマ「睡眠」「ギフテッド教育」に絞って紹介します。
睡眠を削ってはいけない(第二章)
私にとって最も衝撃を受けたのが、この睡眠に関する章です。アメリカでは、睡眠は肥満と共に発達研究の主要テーマとなっていますが、この章では睡眠不足がいかに子どもの健やかな発達に弊害をもたらすかというデータが紹介されています。まず目に止まったのが、「睡眠時間の1時間の損失は認知の発達と成熟の2学年分の損失に相当する」という、テル・アヴィヴ大学のサデー博士とそのチームたちの4、6年生を対象とした研究です。3日に渡って子どもたちを普段より早寝または夜更かしさせ、その後知能検査を受けさせ、結果を比較したものです。眠気を催している6年生は、その学業成績が4年生なみに低下してしまうという驚くべき結果です。
睡眠時間が学業成績に及ぼす多大な影響に関するこの研究結果は、他の研究の結果とも一致しており、特に興味深かったのはミネソタ大学のワーストーム博士による高校生を対象にした研究です。「成績がA評価の生徒はB評価の生徒に比べて睡眠時間が平均15分長く、B評価の生徒はC評価の生徒より平均15分長いという具合に、評価が低くなるにつれて睡眠時間は短くなった」という報告です。私の勝手な想像では、成績の良い生徒ほど、勉強時間が長いため睡眠時間は短くなりそうですが、本の説明によれば、睡眠不足は子どもの脳機能にマイナスに作用し、日中の学習能力低下を引き起こすと考えられています*1。
子どもの睡眠不足は世界的な現象のようです。過密なスケジュール、宿題の増加、テレビやインターネットなど、さまざまな原因が考えられます。日本のように学習塾はなくても、競争社会のアメリカでは、スポーツ、芸術、あるいはアカデミックな分野においてトーナメントやコンテストなどが頻繁に開催され、子どもたちは過密な活動スケジュールの中で過ごしています。たとえば高校でマーチングバンドに参加しているわが息子の場合、月、火、木の放課後に2-3時間の練習、さらに毎週金曜日の夜は、フットボールの高校対抗試合で演奏するため、夜中に帰宅することも珍しくありません。それだけでなく、コンクールや大会などの行事で週末がつぶれることもあります。地域や学区にもよりますが、高校で大学レベルのAP(Advanced Placement)やその一歩手前のPreAPなどの授業を受講する場合、宿題やテスト勉強に多くの時間を割くこととなり、必然的に睡眠時間も減ります。部活の忙しい時期は、夜の就寝が11時過ぎ、朝の起床が5時半というパターンでしょうか。これは本にも書かれている、「ハイスクールでも高学年になると平均睡眠時間は6時間半をわずかに上回る程度で、平均8時間以上寝ている生徒は5パーセントに過ぎない」という睡眠の調査結果と共通しています。
さらに注目に値するのは、ティーンエイジャーはその生理的メカニズムゆえに「夜遅くまで眠れずにいる」という情報です。ティーンエイジャーたちの脳は、夜暗くなっても90分間はメラトニン、すなわち眠気を催させる脳内物質を分泌しないため、10時頃になってもなかなか眠れないというのです。その反動として、朝、学校で居眠りをする生徒たち、さらには車を運転して学校に通う高校生の交通事故が増えます。この調査結果を受けて、ミネソタ州のある学区が始業時間を1時間繰り下げたところ、子どもたちのSAT(大学進学適正試験)の結果がぐーんと上がったそうです。
しかしティーンエイジャーに朝の睡眠が必要であるにもかかわらず、アメリカの高校の始業時間は非常に早いのです。わが息子の高校の場合、始業時間は7時20分です。その時間に合わせて、スクールバスが迎えにくるのが6時半、居住地区によっては朝の6時にバスが迎えるにくることもあります。そうなると起床は、5時あるいは5時半になってしまいます。本にも書いてありますが、スクールバスは第1便で高校生などの年長の生徒をまず学校に送り込み、その後第2便で小中学校などの年少の子どもを送り届けるシステムの学区が多いのです。バスの車両数と運転手を雇う賃金を節約するための学区の予算対策なのでしょうが、それ以外にもトーナメントなどのイベントが多いアメリカの高校の場合、練習や行事に参加する時間を放課後に確保しなければならないという事情もあるでしょう。アメリカの疾病対策予防センターでは、始業時刻の繰り下げを検討するように高校に勧告しているそうです。このテーマについて、米国睡眠財団(US National Sleep Foundation)で大変興味深い記事が紹介されていますので、ご参考までに紹介しておきます。
IQは生まれつきの能力ではない(第五章)
日本ではギフテッド・プログラムは制度化されていませんが、アメリカなどの先進諸国を始めとし、中国や韓国などのアジア諸国に至るまで幅広く浸透しています。ギフテッドというのは、平均よりも顕著に高い能力を持っている人のことを指します。以前、チャイルド・リサーチ・ネットに掲載された拙論文「アメリカのギフテッド教育事情」にも書きましたが、ギフテッドの判定資料として最も一般的に用いられるのが、知能指数(IQ)検査です。
この章で繰り返し強調されているのは、幼児を対象とした知能検査が子どもの学力を予測する判断材料としてはあまり役立たないという内容です。たとえば知能検査が将来の学業成績をどのくらい予測するかということを44の研究論文をもとにメタ分析を行ったペンシルバニア州立大学のスエン博士によると、就学前の知能検査とその後の学力検査の相関関係は平均して40%くらいしか存在しないそうです。アメリカ、カナダ、イギリスの合計3万4000人の子どもを対象とした縦断研究の結果でも、就学前の知能テストあるいはアチーブメントテストと後の学業成績の相関は、よくて40%だということが報告されています。
このように幼児期の知能指数がのちの成績にはっきりとは結びつかないとするなら、ギフテッド・プログラムの参加に「拾いすぎた(誤って肯定的に判定した)子どもと、見落とした(誤って否定的に判定した)子ども」たちがいるという問題が浮かび上がります。これは、ギフテッド・プログラムへの選抜試験を就学前の子どもを対象に行っている学区では、大器晩成型の子どもたちが、ギフテッド教育を受けるチャンスを逃してしまう可能性があることも考えられるのです。
また、一度ギフテッド・プログラムに参加を認められた子どもは、現在のアメリカ教育のシステムでは、再試験を受けることなく、ずっとギフテッドのクラスに残留できるという実態が浮き彫りになっています。アメリカに根強くある、知能は生得のもので、変動することはないという認識に、作者らは疑問を投げかけています。
私事で大変恐縮ですが、娘はある私学附属のプレスクールに入園する手続きの一環として、4歳の終わりに発達テスト(Developmental Indicators for the Assessment of Learning - Third Edition (DIAL-3))を受けました。このプレスクールは、ギフテッド教育とはまったく関係がなく、ピアジェの構成主義に基づいた保育実践で知られている園でした。テストの結果、娘は認知面と運動感覚機能の面でやや遅れがみられると診断され、Title 1 Preschoolという州政府管轄の発達に遅れがみられる就学前児のための補償プログラムを紹介されることになりました。試験官とのやりとりを回想してみると、「アルファベットを言ってみてください」「あなたのミドルネームは何ですか?」「お友達におもちゃを借りて壊したらどうしますか?」などの質問に対して、答えに戸惑ったり、ちんぷんかんな答えを返していたように記憶します。
今考えると、娘がこのような質問に答えられなかったのは、私の日本式子育ての影響も若干ながらあるのではないかと思うのです。母子交渉の日米比較に関する先行研究の中では、アメリカの母親に比べて日本の母親は子どもの知的発達を促す言語的刺激が乏しい、あるいは少ないということが報告されています。日米発達比較研究の第一人者である東洋氏も、著書の中で、日本の母親はあまり教えない、またあまり教えるべきではないというタテマエをもっているようだということを書いています。一方、アメリカの母親、特にいわゆる中流知識階級の母親は、説明的かつ語彙豊かに子どもに言葉かけをする場合が多いのです。アメリカで感じたカルチャーショックの一つが、このアメリカ人の母親たちの子どもへの言語的はたらきかけでした。動物園やチルドレン・ミュージアムなどの公共の場へ足を運ぶ度に、アメリカの母親たちはわが子を目の前にミニ講義をしているのではないかと思ったくらいです。
この文化差は、フランスで子育てをした体験をもとに書かれたベストセラー本、『Bringing up Bébé: One American mother discovers the wisdom of French parenting』の中でも示されています。著者はニューヨークの公園を訪れた時に、中流知識階級の母親たちが、自分の子どもに対してノンストップで話しかけている光景を目にし、びっくりしたそうです。子どもが今行っている行動に対して、ナレーターのように説明することで、語彙を膨らまし知的刺激を与えるという目的のようですが、フランスには見られない光景だと説明しています。このように、フランスと比較してもやはりアメリカの母親は、子どもの知的発達を促すために、早い時期より言語的刺激を与える傾向にあるようです*2。そう考えると幼児期ほど、知能検査はこのような教育環境の社会文化差にある程度左右されるのではないでしょうか。ギフテッド・プログラムの参加者が、マイノリティでなく、白人に大きく偏っているというのも理解できるように思います。一時は「発達遅れ」と診断されたわが娘が、その後ギフテッド・プログラムに参加するようになったのも、幼児の知能が把握しにくいものであることの一例だと思います。
最近の脳科学の知見によれば、知的処理の領域が脳内で移動していると、『NurtureShock』の中で述べられています。子どもが小さい頃は、言語の知識をつかさどる左半球の領域の発達が進みますが、高次元の推論に必要とされる前頭前野の皮質は、脳の中でも成熟が一番遅い領域であり、思春期直前までアップグレードする(さらに高性能なものと切り替わる)ことがないそうです。「子どもが最終的に知的な面で成功収められるか否は、知的処理をより効率のよいネットワークにシフトすることを脳がどこまで学習できるかによって、大きく左右される」と筆者らは説明しています。その一例として、ソウル国立大学のリー博士が韓国の高校生を対象に行った脳処理に関する実験が挙げられています。優秀な生徒たちは情報処理を前頂葉系のネットワークにシフトさせていたそうですが、普通の生徒たちはこのような脳のシフトが見られなかったそうです。結局のところ、子どもたちのギフテッド教育のふるいわけを、その知能が正確に明らかになる時期、せめて小学校3年生まで待ったほうがよいのではないかということです。日本の中ではギフテッド教育はまだ導入されていませんが、このようなアメリカにおけるギフテッド・プログラムの選抜、開始時期をめぐるコンセンサスを参考にしつつ、子どもたちの潜在能力を伸ばすためにどのような教育的な介入が必要なのかを前向きに検討して欲しいと思います。
おわりに
子育ての本は数多く出版されていますが、専門家の「こうであるべき」という助言で終わってしまうことが多いものです。この本には、一般的あるいは本能的に自分が正しいと思っていた子育ての方法について、それを覆す、読者の盲点をつくような提言にぐいぐい引き込まれていく面白さがあります。また、それぞれのトピックについて膨大な量の実証研究が分かりやすく紹介されていることから、読んでいても納得がいきます。読み進めながら、ああでもないこうでもない、と自分の中に対話が生まれてくるとも言えるでしょう。そういった意味で、親の子育ての主体性を高め、真の意味で親の成長を助けてくれる本と評価できるのではないかと思います。
- *1 睡眠不足と学業の関係について、2012年に学術専門誌『Child Development』より掲載されたUCLAの研究者らによるアメリカの高校生を対象とした研究によると、勉強のために睡眠を犠牲にする場合、翌日の授業内容の理解、宿題、テストなどに悪影響を及ぼすという結果が報告されている。またこの傾向は学年が上がるにつれて、さらに強くなるという警告を発している。
Gillen-O'Neel, C., Huynh, V. W., & Fuligni, A. J. (2012). To study or to sleep?: The academic costs of extra studying at the expense of sleep. Child Development, 84(1), 133-142. - *2 乳児の親のインタビューを比較した国際研究の中でも、アメリカの親は、他国の親(イタリア、韓国、スペイン、オランダ)と比較して子どもの認知的な経験を高めるような刺激を与える傾向が非常に高いということが報告されている。
Harkness, S., Super, C. M., Moscardino, U., Rha, J.-H., Blom, M. J. M., Huitron, B., et al. (2007). Cultural models and developmental agendas. Journal of Developmental Processes, 2, 5-39.
参考文献
- 東洋 (2004).日本人のしつけと教育―発達の日米比較にもとづいてー 東京大学出版社
- Branson, P., & Merryman, A. (2011). 間違いだらけの子育て―子育ての常識を変える10の最新ルール(小松淳子、訳)、東京:インターシフト.(Bronson, P., & Merryman, A. (2009). NurtureShock: New thinking about children. New York : Twelve)
- Druckerman, P. (2012). Bringing up Bébé: One American mother discovers the wisdom of French parenting. New York: The Penguin Press



 ポーター 倫子(Noriko Porter)
ポーター 倫子(Noriko Porter)










