社会の注目度や取り組みにより変わる認知件数
いじめの認知件数は、いじめの発生件数そのものではありません。いじめの発生件数自体は、年度間や自治体間で、さほど大きく異なるとは推測しがたいですが、いじめの認知件数は年度によっても大きく異なり、自治体間の差も非常に大きいものです。
実際に地域間や年度間の差はどれくらい大きいのでしょうか。児童生徒1000人あたりのいじめ認知件数について、表1には各都道府県別の推移を示し、図1には平成20年度から平成24年度にかけての各地域別の推移を示しました(平成23年度から24年度にかけて、九州地域が急増していますが、これは表1を見ても明らかなように、鹿児島県での認知件数の急増を反映したものです)。平成19年にいじめの定義の変化(第1回を参照)を受けて、認知件数が急増したため、平成19年度よりも前のデータを入れると、さらにめまぐるしくなってしまうので、表1には平成19年度から平成25年度までのデータを示しています。図1をご覧になってわかるように、平成23年度から24年度にかけて大きく認知件数も上がっていますので、表1に示す都道府県のうち23年度から24年度にかけて10倍以上数値が上昇した部分には赤字とピンク色の背景をつけ、5倍以上10倍未満の間で増加した箇所は赤字で示しています。
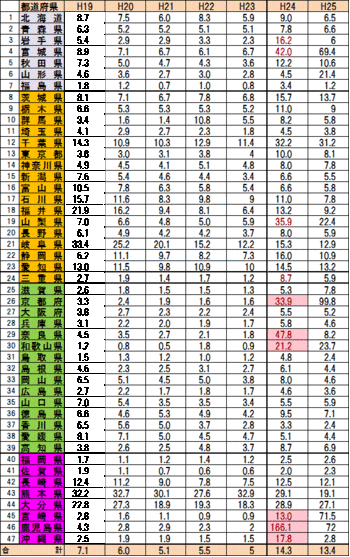 | 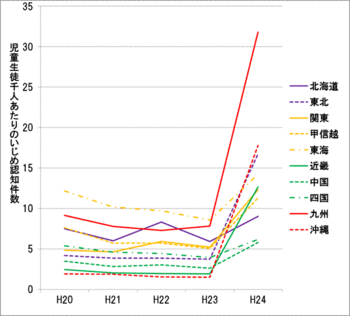 ※クリックで拡大 |
| (左)表1.児童生徒1000人あたりのいじめ認知件数(都道府県別) (右)図1.児童生徒1000人あたりのいじめ認知件数の地域別年次推移 | |
過去にも、大きないじめ事件によりいじめへの社会的関心が上がったり、それをうけて文部科学省のいじめの定義や対策が変わったりすると、いじめの認知件数も増大する傾向がありました。たとえば、平成23年に社会問題となった大津いじめ自殺事件の後、学校でのいじめ発見のアンケート実施率や取り組みが高まり、いじめの認知件数は、平成23年度の全国平均1000人に5人から、平成24年度は14.3人まで3倍近く増加しています。また、地域差で見ると、人口1000人あたりのいじめ件数の最小と最大が、平成23年度は佐賀県の0.6人、福島県の0.8人、和歌山県と宮崎県の0.9人から熊本県の32.9人までの分布だったのに対し、大津のいじめ事件後の平成24年度は、佐賀県の2.0人(23年度の3.3倍)、福島県の3.4人(23年度の4.3倍)から、鹿児島県の166.1人(23年度の2人の83倍)と、激しく増えています。大津の事件があった滋賀県近県で23年度と24年度の比較を見ると、滋賀県は1.3人から5.3人へと4倍の変化でしたが、隣の京都府では1.6人から33.9人へと20倍あまりの増加、奈良県でも1.8人から47.8人へと25倍あまりの増加でした。
学校や自治体からすれば、いじめの認知件数が多いと、「いじめ多発地域」あるいは「いじめへの取り組みがしっかりしていない」と見られる風評被害のおそれもあるので、認知件数が少ない方が世間体は良いから、できれば認知件数を少なくしたいという気持ちが働きやすいだろうと思われます。そうした中で、多い認知件数を示すのは勇気がいることですから、認知件数が増えるということは、学校側のいじめへの取り組み姿勢が高まったことなどを反映している可能性も高く、学校や自治体のいじめ対策への熱心さの表れとみるべきでしょう。ただし、いじめの認知件数が低いということが、取り組みの不熱心さを示すというものではない点にも注意が必要です。認知件数が低いのは、熱心な取り組みを行って効果を上げているから、というところもたくさんあるからです *。
教職員の問題行動といじめ認知件数の関連:
教職員のコンプライアンスが低いほど、いじめ認知率が少ない?
認知件数が少ないことは、実際にいじめ対策がうまくいっていることを示すものでもあるかもしれませんが、この認知件数の少なさが、「自治体や学校レベルの対応の消極性や教員の問題意識の低さを反映している」可能性を否定しきるだけのデータもありません。そこで、「教職員の問題行動の発生率が高い(コンプライアンスが低い、と言えるかもしれません)都道府県ほどいじめの認知件数が少ない」という仮説を検証してみました。この仮説は、私の研究室で研究員をしていた高史明(たかふみあき)氏と考え、高氏と大学院生の金勝明花さんがデータの収集と分析をしたものです。
この研究は、2つの研究からなっています。文部科学省のデータ(いじめの認知率、教職員の処分率、処分の重さ)に基づいて検証したのが研究1で、文部科学省のデータのほかに、文科省と利害関係があまりない法務省のデータを用いたのが研究2です。
研究1:文部科学省のデータを用いた分析
文部科学省が公表済みの平成19年から平成25年度までの統計に基づき、都道府県別に (1) 児童・生徒数あたりのいじめの認知件数の比率("認知率")、(2) 教職員数あたりの処分教員数の比率("処分率")、(3) 教職員の処分に占める懲戒処分(重い処分)の比率("懲戒比")、を算出しました。
統計的な分析を行った結果、次のようなことがわかりました(具体的な統計分析は、教職員の処分についての年度別データ及び都道府県ごとの平均の主効果および交互作用、2012年 [大津の事件による社会的関心の増加] 以後であるか否かを示すダミー変数を説明変数とする階層線形モデルを検討しました。さらに、都道府県レベルの処分率と懲戒比の交互作用が有意だったため単純傾斜を検討しました)。
まず、教職員が処分される際に比較的軽微な処分で済まされることが多い(懲戒比が低い)場合、処分率が高いほどいじめの認知率が低いことがわかりました。また、重い処分が多い(懲戒比が高い)場合には処分率の高さといじめ認知率には関連が見られませんでした。
研究2:文部科学省と法務省のデータを用いた分析
研究1で用いた教員の処分についての統計はそれ自体が教育委員会等の裁量を反映した数値であり、処分率が高いことがむしろ、コンプライアンスを保とうとする自治体の努力を反映している可能性もあります。そこで研究2では法務局への人権救済の相談件数(教職員が不適切な行為を行い、かつ学校や教育委員会の対応にも満足しなかった事案数を反映する)を説明変数とし、研究1と同様の分析を行いました。
具体的には、"認知率"に加えて、文部科学省および法務省の統計より (1) 児童・生徒数あたりのいじめについての相談件数の比率("いじめ相談率")、(2) 教員数あたりの体罰についての相談件数の比率("体罰相談率")、(3) 教員数あたりの体罰以外の人権侵犯への相談件数の比率("その他相談率")を算出し、研究1と同様に分析しました。
変数間の関連性を見るための統計分析(ここでは、階層線形モデルという分析法を使いました)結果から、体罰についての相談件数が多い都道府県ほどいじめの認知件数は少なくなるという結果が得られました。
ただし、研究1も研究2も、「教職員の処分率が高いほど、いじめ認知率が下がるという統計的に意味のある傾向が見られた」ことを示していますが、「教職員の処分率が高いと、必ずいじめ認知率が下がる」とか、「いじめ認知率が低い都道府県は、必ず教職員の処分率が高い」ことを示すものではありません。教職員を厳重に処分しようとする都道府県は、それ自体がコンプライアンスの高さを示しているかもしれませんし、その場合はいじめ対策にも熱心かもしれません。また、研究1では、処分が重い都道府県に関しては、教職員の処分率といじめ認知率には関係がないことが示されています。研究2では、教員からの体罰などの人権侵害に関する法務局への人権相談が多いほど、いじめ認知率が低いという傾向(いじめ認知率が低い都道府県では教員の体罰が多いことを示すものではありません。そうでない傾向の都道府県が多い中に、そういう傾向のある都道府県も混じっているかもしれない、というくらいの効果です)も見られましたので、教員の体罰などが多い場合には、教員のいじめに対する感受性も下がり、いじめを見過ごしやすくなったり、あるいは体罰を教員が行うこと自体がいじめの問題を過小視させることにつながり、いじめ問題を助長する可能性も含むかもしれません。
以上のほかにも、都道府県別の年次推移のデータは、様々な観点から読んでいく必要のあるもので、実際に数値を出していくプロセスや、当事者の皆さんの判断について具体的に知らないと、大きな読み違いを犯してしまう可能性をもっていると言えるでしょう。
- * やや理屈っぽい話になりますが、「A(認知件数が多い)ならばB(取り組み熱心)」という命題は、「Aでない(認知件数が少ない)ならばBでない(取り組み不熱心)」を意味するものではありません。なぜなら、「AならばB」というのは、「Bの中にAが含まれる」のであって、「B(取り組み熱心)の中にA(認知件数が多い)が含まれていさえすれば、Aでないもの(認知件数が少ない)も含まれていてもかまわない」ことを意味するからです。「AならばB」から、「AでないならばBでない」と主張するのは論理的誤謬(誤り)です。論理学では、「AならばBである」という命題のなかの、Aを前件、Bを後件というので、前件否定の誤謬などと言いますが、「AならばBである」という前提から、「AでないからBではない」という結論を導いてしまう、この前件否定の誤謬は、教育論でもいろんなところで見られる、なじみ深い誤りではないでしょうか。



 杉森 伸吉 (すぎもり・しんきち)
杉森 伸吉 (すぎもり・しんきち)










